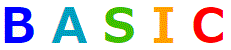
十進BASICプログラミングについての質問や研究成果の公開にご利用ください。
メッセージ入力枠は右下をドラッグして拡大できます。 画像,URLは省略可能です。
編集/削除キーを入力しなくてもエラーにはなりませんが,何か適当な半角英数字4~8文字を指定してください。
特に,長文投稿の場合,プレビューで最後の行を確認しても,実際には途中で切れてしまうことがあるので,投稿後の確認が必要です。
Raspberry Pi GPIO - SHIRAISHI Kazuo
2025/08/14 (Thu) 10:55:55
Raspberry Pi OS のRaspbianでGPIOを仮想ファイルとして扱うので試してみました。
https://tool-lab.com/raspi-gpio-controlling-command-1/
を参考にしました。
GPIO4にLEDを,GPIO5にスイッチを接続しています。
/sys/class/gpio/exportに4を書き込みとGPIO4が使用可能となるので,
OPEN #1:NAME "/sys/class/gpio/export",ACCESS OUTPUT
PRINT #1:4
CLOSE #1
としてみたのですが,機能しませんでした。
100行のようにechoコマンドを実行することで済ませています。
echoコマンドはbashの内部コマンドなので,echoをEXECUTE文で呼び出すことはできません。
100 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 4 >/sys/class/gpio/export")
110 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 5 >/sys/class/gpio/export")
120 WAIT DELAY 0.1
130 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo out >/sys/class/gpio/gpio4/direction")
140 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo in >/sys/class/gpio/gpio5/direction")
150 OPEN #4:NAME "/sys/class/gpio/gpio4/value", ACCESS OUTPUT
160 FOR i=1 TO 20
170 PRINT #4:STR$(MOD(i,2))
180 OPEN #5:NAME "/sys/class/gpio/gpio5/value", ACCESS INPUT
190 INPUT #5:s$
200 CLOSE #5
210 PRINT s$
220 WAIT DELAY 0.5
230 NEXT I
240 CLOSE #4
250 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 4 >/sys/class/gpio/unexport")
260 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 5 >/sys/class/gpio/unexport")
270 END
130行,140行は,
OPEN #2:NAME "/sys/class/gpio/gpio4/direction", ACCESS OUTPUT
PRINT #2:"out"
CLOSE #2
OPEN #3:NAME "/sys/class/gpio/gpio5/direction", ACCESS OUTPUT
PRINT #3:"in"
CLOSE #3
のようにしても大丈夫でした。
出力は/sys/class/gpio/gpio4/valueに"0"または"1"を書き込むのですが,それは,150行,170行のように実行可能でした。
入力は,180~200行のように毎度OPEN~CLOSEを実行しないと読み込めませんでした。
Re: Raspberry Pi GPIO Raspberry PI OS Bookworm - SHIRAISHI Kazuo
2025/08/14 (Thu) 11:11:15
Raspberry Pi OS Bookwormだと,GPIOの番号が変わってしまうそうです。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01109/040700054/?P=2
に従って,
cat /sys/kernel/debug/gpio
を実行して調べてみると,私のRaspberry Piでは,GPIO4,5の番号は,それぞれ,516,517に変更されていました。
次のように書き換えると実行可能でした。
100 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 516 >/sys/class/gpio/export")
110 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 517 >/sys/class/gpio/export")
120 WAIT DELAY 0.1
130 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo out >/sys/class/gpio/gpio516/direction")
140 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo in >/sys/class/gpio/gpio517/direction")
150 OPEN #4:NAME "/sys/class/gpio/gpio516/value", ACCESS OUTPUT
160 FOR i=1 TO 20
170 PRINT #4:STR$(MOD(i,2))
180 OPEN #5:NAME "/sys/class/gpio/gpio517/value", ACCESS INPUT
190 INPUT #5:s$
200 CLOSE #5
210 PRINT s$
220 WAIT DELAY 0.5
230 NEXT I
240 CLOSE #4
250 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 516 >/sys/class/gpio/unexport")
260 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "echo 517 >/sys/class/gpio/unexport")
270 END
Re: Raspberry Pi GPIO - SHIRAISHI Kazuo
2025/08/14 (Thu) 13:23:01
https://pip.raspberrypi.com/categories/685-whitepapers-app-notes/documents/RP-006553-WP/A-history-of-GPIO-usage-on-Raspberry-Pi-devices-and-current-best-practices.pdf
によると,/sys/class/gpio/は廃止予定で,替わりにlibgpiodを使えという。
Intel CPU版で利用可能なDLL呼び出し
https://decimalbasic.web.fc2.com/ExtDLL.htm
をARM64でも実行できるように準備中ですが,とりあえず,
https://qiita.com/ma2shita/items/d745a8f89c673fd74a5e
を参考にpinctrlコマンドでアクセスするプログラムを作ってみました。
100 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "pinctrl set 5 ip pd") !gpio5を入力に変更
110 FOR i=1 TO 20
120 IF MOD(i,2)=1 THEN
130 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "pinctrl set 4 op dh")
140 ELSE
150 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "pinctrl set 4 op dl")
160 END IF
170 EXECUTE "/bin/bash" WITH ("-c", "pinctrl get 5 >gpio5.txt")
180 WAIT DELAY 0.25
190 OPEN #1:NAME "gpio5.txt"
200 LINE INPUT #1:s$
210 PRINT s$
220 !ERASE #1
230 CLOSE #1
240 WAIT DELAY 0.25
250 NEXT i
260 END
pinctrlは独立コマンドなのでEXECUTE文で直接実行可能ですが,データ入力にはコマンドからの返答を取り込む必要があるので,
170行のようにファイル(gpio5.txt)を介してデータを受け取ることにします。そのため,bashを介しての実行になっています。
220行のERASE文は不要だったようです(追記されるのでなく,書き込み時毎度リセットされる)。
受け取ったデータは,次のようになっています。
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | lo // GPIO5 = input
5: ip -- | lo // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | lo // GPIO5 = input
5: ip -- | lo // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
5: ip -- | hi // GPIO5 = input
スイッチの操作でhiとloが切り替わっています。
Re: Raspberry Pi GPIO - SHIRAISHI Kazuo
2025/08/18 (Mon) 15:16:25
DLL呼び出しが可能になるように拡張しました(Ver.0.7.6.2,および Ver.0.9.2.6)。
Qiitaの記事
https://qiita.com/wancom/items/b041ee7408a87fabf48e
を参考にlibgpiod呼び出しに書き換えてみました。
事前に
sudo apt install libgpiod2 libgpiod-dev libgpiod-doc
を実行して,libgpiodをインストールしておいてください。
100 ! sudo apt install libgpiod2 libgpiod-dev libgpiod-doc
110 ! /usr/share/doc/libgpiod-dev/html
120 OPTION ARITHMETIC NATIVE
130 FUNCTION GPIOD_CHIP_OPEN_LOOKUP(s$)
140 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_chip_open_lookup"
150 END FUNCTION
160 FUNCTION gpiod_chip_get_line(n,t)
170 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_chip_get_line"
180 END FUNCTION
190 SUB gpiod_line_request_output(n,s$,t)
200 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_line_request_output"
210 END SUB
220 SUB gpiod_line_request_input(n,s$)
230 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_line_request_input"
240 END SUB
250 SUB gpiod_line_set_value(gpio, x)
260 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_line_set_value"
270 END SUB
280 FUNCTION gpiod_line_get_value(gpio)
290 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_line_get_value"
300 END FUNCTION
310 SUB ppiod_chip_close(gchip)
320 ASSIGN "libgpiod.so","gpiod_chip_close"
330 END SUB
340 LET GChip=GPIOD_CHIP_OPEN_LOOKUP(STR$(0))
350 ! PRINT GChip
360 LET gpio4 = gpiod_chip_get_line(GChip, 4)
370 ! PRINT gpio4
380 LET gpio5 = gpiod_chip_get_line(GChip, 5)
390 ! PRINT gpio5
400 CALL gpiod_line_request_output(gpio4, "LED", 0)
410 CALL gpiod_line_request_input(gpio5,"Switch")
420 FOR i=1 TO 20
430 CALL gpiod_line_set_value(gpio4, MOD(i,2))
440 WAIT DELAY 0.25
450 PRINT gpiod_line_get_value(gpio5)
460 WAIT DELAY 0.25
470 NEXT i
480 CALL ppiod_chip_close(GChip)
490 END
参考例(Qiitaの記事)では gpiod_chip_open_lookup の引数が""になっていますが,ASSIGN文で定義されるDLLに空文字列を指定するとヌルポインタが渡されるので,
空文字列への(ヌルでない)ポインタを渡すために340行ではchr$(0)を指定します。
"/dev/gpiochip4"のようなデバイス名を指定すべきところだと思いますが,OSがBullseyeだと/devにそれらしきデバイス名が出て来ないのですが,chr$(0)を指定すると動作します。
また,gpiod_chip_open_lookup が返す値はポインタですが,十進BASICでは2進モードでも53ビットの精度しかないので,64ビット環境だと使えない可能性があります。
350行の ! を削除してその値が53ビットの範囲にあることの確認が必要です。
ただし,64ビットのポインタは下位3ビットが0であるのが普通なので,2^56以下であれば可かも知れません。
400行,410行の"LED","Switch"は,使い道が不明ですが,適当に付けた名前です。
libgpoidの詳細は,
/usr/share/doc/libgpiod-dev/html/modules.html
にあります。とりあえず
/usr/share/doc/libgpiod-dev/html/group__line__request.html
/usr/share/doc/libgpiod-dev/html/group__line__value.html
あたりを見てください。
上の例は上記文書を読みこなしていない状態で作成したものです。とりあえず動作する参考例にしてください。